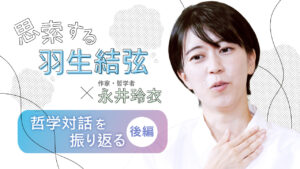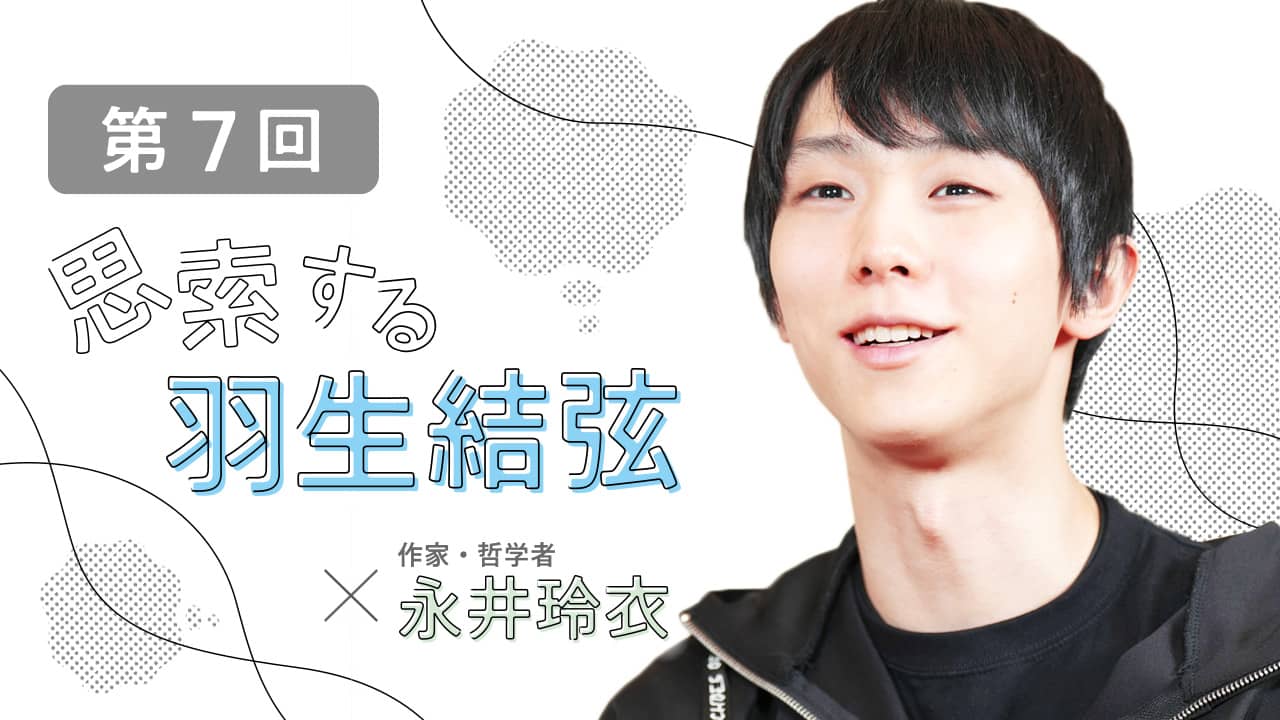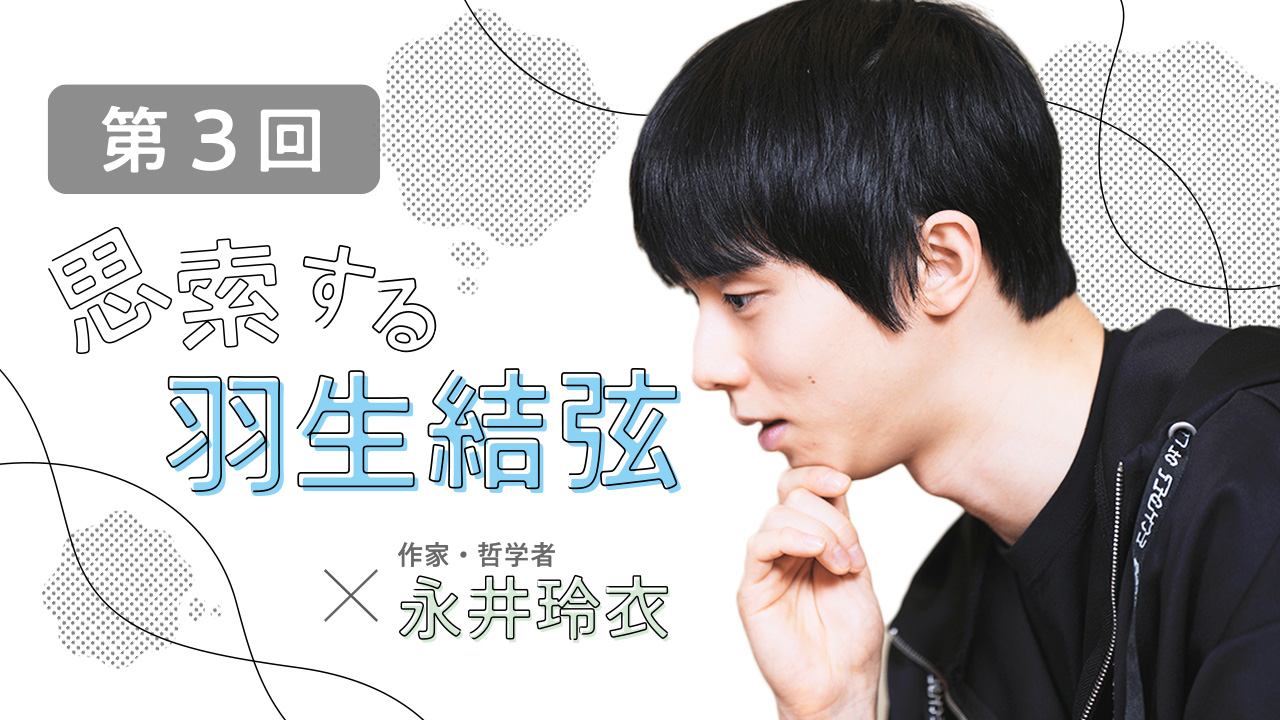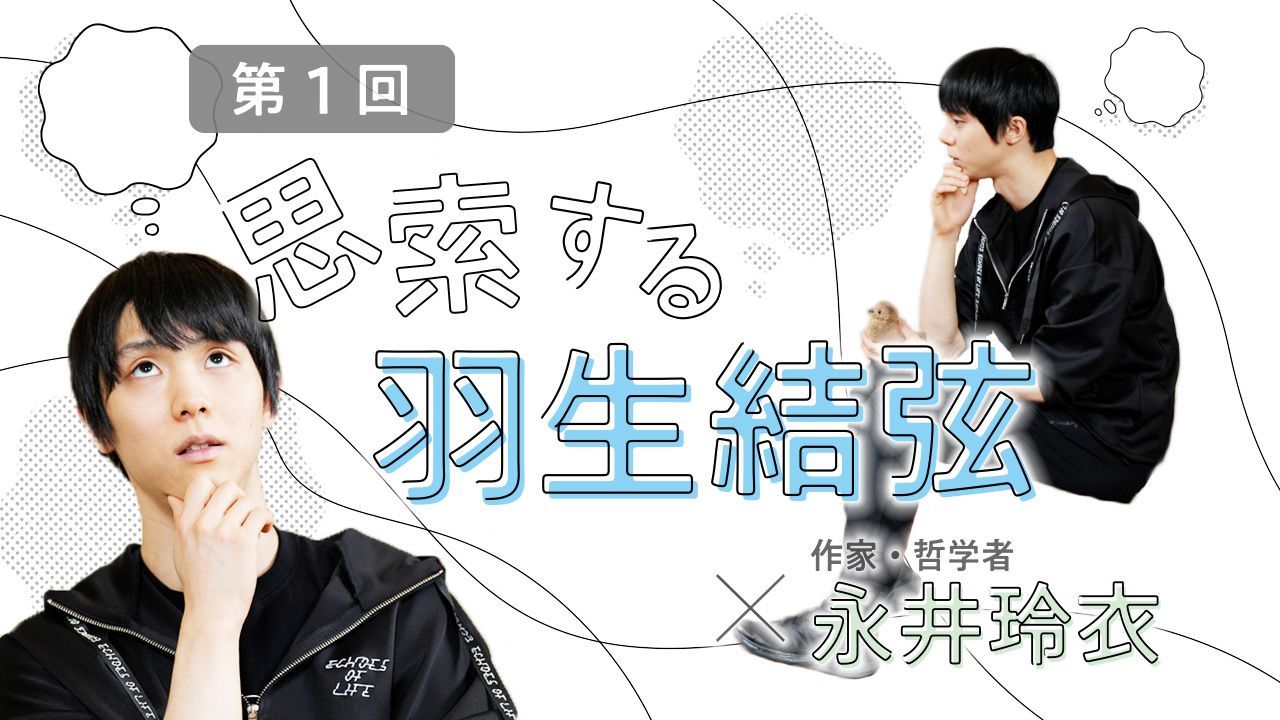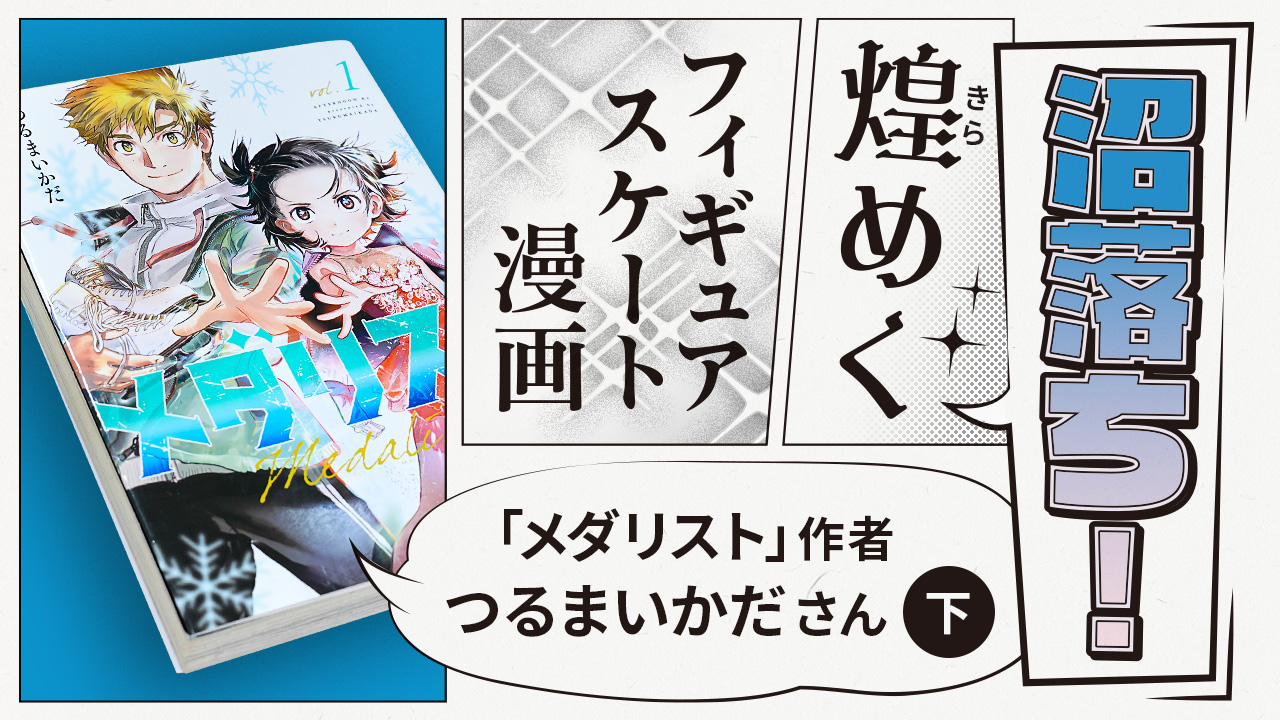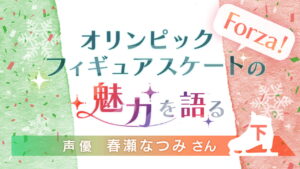「まえがみ」さんこと、フィギュアスケーターの羽生結弦さんと、「ねぐせ」さんこと、作家で哲学者の永井玲衣さんが日頃のもやもやや問いを聞き合い、語り合った哲学対話企画「思索する羽生結弦」。連載の中で互いに問いを聞き合い、言葉を探り出していく2人の姿に、読者の方が触発され、対話の参加者のようにSNSにご自身の問いや思いを投稿してくださいました。
そんな皆さんのお考えをお聞きしたいと、感想を募ったところ、たくさんの回答をいただきました。どの言葉も丁寧に紡いでくださっていることが伝わってきました。ありがとうございました。
その内容を永井さんのコメントとともに感想編としてお伝えします。
※記事でご紹介させていただいたご感想は、個人が特定される恐れがある場合や編集の都合により、文脈を損ねない範囲で一部抜粋した形でご紹介しています。
体験や自分のあり方に照らす
―いただいた感想を読んで、どんなことを感じましたか?
今回の連載を読んで、自分もいろいろ考えたりしてたけど、そういう考えを押し込めちゃったりしてたなって振り返ってくださったり、連載を読んで対話を諦めなくてもいいんだなって、自分自身の体験や、これまでのご自身のあり方に引き付けて考えてくださったりした方が多くて、それがすごく印象的で、うれしかったですね。
読んで面白かったですっていうのもうれしいし、自分はどうなんだろうとか、自分の頭もぐるぐる動かしてくださった方が多かったのかなっていうのは印象的でしたね。
▶最も多かった感想は、羽生さんの発想や言葉の豊かさや思考の深さを称える声でした。それと同時に哲学対話そのものを面白がり、感情や経験に照らした言葉をつづってくださった方もいらっしゃいました。
【こころさん】
この感情を言葉にするのはとても難しいのですが、 一言で言うと、もんもんとする笑でしょうか。
読んでいるうちにその場にいるような感覚になってきたにも関わらず、実はその場に居ないことに悔しさに似た感情が生まれました。
もちろん、私は羽生結弦さんのファンなのですが、ここは結弦さんとではなく、「まえがみさん」と「ねぐせさん」と小鳥を渡し合って、水中に潜りたい!哲学対話をしたい!と思いました。
この対談を読んでもう一つ気づいたのは、以前から私は、もうひとりの「私」と哲学対話をしているかもしれないということです。 仕事柄、電車やバスで移動することが多いのですが、大抵はもう一人の私と対話しているような気がします。 なので、「水中の哲学者たち」を読んでいると、対話する人が急に増えたようで、楽しいやら、恥ずかしいやらで忙しい感情になりました。
【和紅茶さん】
お二人の思考はどんな方向に向かっていくのだろうとワクワクしながら読みました。 わたしがこの場にいたとしても、何かしら理解して一言でも発言できるかなあ…と少し頼りなく思いながら。 わたし自身は問いをもつことなどまるでありません。読んでは考え、考えて全部を読むには時間がかかりました。
羽生選手は永井さんとの対話の中で思考を巡らせ言葉を紡いでいく様子が楽しそうでした。ホワイトボードに書き出されたたくさんの問いの中に共通するものを見出そうとする視点(編集部注※連載第4回)には、[そんな見方があるのか]と驚きました。
羽生選手の言葉の使い方は秀逸です。 [プロ転向] [メンテナンス期間] 言葉選びをありきたりで済まさず、自分の意思を明確に示そうとするところがすごいのです。どこをどうしたらこんな発想が出てくるのか。その秘密が垣間見えたような気がしました。
問いをもつ…とは、当たり前を疑うことなのかな? 問いとは、苦しいときや違和感を感じるときに出てくるものかもしれない…とも思いました。永井さんがさまざまな場所で哲学対話をする意味はそこにあるのかもしれません。そう考えたとき、問いなんて何もないと思い込んでいたわたしにも一つ、問いが浮かんできました。そして、問いへの答えはすぐに見つかるはずもなく悶々と…水中を潜っていく気持ちが少しわかったかもしれません。
問うことによって、うっすら暗闇の中にいた気分にわずかに灯りがともったようにも感じました。 わたしからは遠いところにあると思い込んでいた[問い]に、少しだけ近づけたように思いました。
【こあらさん】
初めて哲学の扉に触れさせていただけたように思いました。もんもんとしていいんだ… もやもやを抱えたままでいいんだ…との言葉も今までの人生を応援されたようでうれしいかったです。
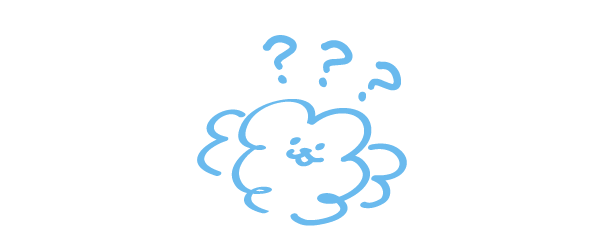
見えなかったものが見えてくる
▶永井さんの哲学対話では、さまざまに出た問いや考えを対話の最後に、こういうことだったという風に一つに結論づけません(連載6回目)。対談の記事としてはあまり見ない形でしたが、そうした形式を前向きに受け止める声もありました。
【あおいとりさん】
話すとき結果を出してまとめてしまいたくなるけれど、こんなふうにただ潜ってそれを出していくというやり方があるんだなと驚きました。毎回モヤモヤしましたが(笑)羽生さんの潜りが深いので何度も読み返して、でもわからなくて…そして私も自分の世界があるんだと感じました。
【ダメージさん】
正誤を探ってしまいがち、「人それぞれ」でまとめてしまいがち、しかも「オチは?」となってしまいがち関西人。 無限に広がる深まる思考や会話は好きなのに、これまでそんなふうにやってしまいがちだったけど、すぐに答えは出なくて悶々としてもいい、深く考えてもいい。でも時間が来たらスパッと終了。このスパッと終了システムが私にとってすごく大事だなと思いました。
そんな思索の取っ掛りと潜る方法を 永井さんと羽生さんとのやり取りから教えてもらった気がします。 問いと問いからの思索で水中に潜って、足を取られたり息苦しくなることもあったりするかもだけど、初めて見るものや美しいものや珍しいもの意外なものなどたくさん見れるといいなと思いました。
―こうした感想を読んで、結論って、どうしてみんな窮屈に感じるのか。結論って何なんだろうと思ったのですが、結論ということについて考えていらっしゃることってありますか?
哲学対話って「答えはないですもんね」みたいに言われることがあります。「答えなんかないよね」として対話をしているのではなく、何かに向かって探求はしているんですよね。今回、いわゆる結論めいたことを対話の最後にまとめてしまわないっていうことが、たぶんみなさん新鮮だったと思うんですよ。
じゃあ、対話の中で何も得られませんでしたかっていうと、そうではない。対話の1時間半や2時間の中で、これまで見えなかったものが大量に見えるようになっているはずなんですよね。そういうことを得ていると思うんです。
いわゆる結論というか、まとめるって何なのか? 実際に自分自身が話す中でのもがきだったり、言葉を探すために黙ったりすることもある。なんとか絞り出して、言葉にしてみる。でもまとめるっていうのは、そういったもの全てを遮障しちゃう行為なんですよね。
対話の中で、みんなであっちに行ったり、こっちに行ったり、見えなかったものを見えるようにして、シンプルだと思っていた世界がどんどん複雑になって、不安にもなるけれど、豊かになっていく。せっかく、そうした豊かさの中に入っていったのに、例えば、「愛ってかけがえがないものって分かりましたね」といった感じでまとめてしまうと、シンプルな世界に引き戻しちゃうことになる。
結論がないことがすごく刺激的だっておっしゃるのは、多分みなさん、何でそんな風にまとめちゃうの? もっといろいろあるのにっていう思いがたぶんあるからだと思うんですよね。 今回の哲学対話で、みんなちょっと解放された気持ちになったのかなって想像しました。
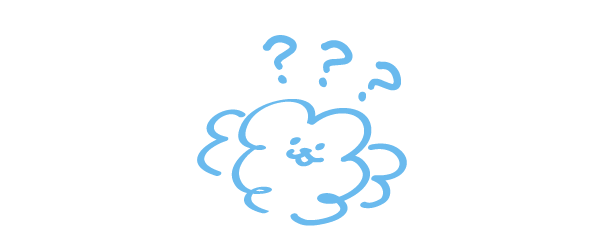
対話を読んでいて迷子に、問いは怖い?
▶連載の内容が難しかったという感想も複数ありました。
【靴下さん】
正直な感想を申し上げると、恥ずかしながら頭の中はパンクしています。 特に第6回(編集部注※連載6回目)ではかなり迷子になってしまいました。それは恐らく、自分が『問い』というものに怖さを感じているから、ある種の拒絶反応のようなものなのかもと思いました。(こんなことを言ってしまうと対話に参加された皆様にも企画された皆様にも申し訳ないですが…)
これはもちろん、否定的な感想ではありませんので!読み物として本当に面白かったのですし、羽生選手の心の内を少し垣間見れたような気持ちにもなり、一読者としてとても有意義な時間になりました。
目に映るもの、聞こえてくる言葉たち、過ぎていく今日…今まで水の流れのようにやり過ごしてきたものたちに、ちょっと立ち止まって思いを乗せてみようか、そういう気持ちにもさせてくれる連載でした。
―難しいことにどう向き合えばよいでしょうか?
わたしたちの社会は、「共感」とか「わかりやすい」ということがあまりに求められていて、「難しいけどききたい」とか「わからないからこそ考え続ける」のようなことの価値が低くなっているかもしれません。
でも難しいと感じることは当たり前だし、それが「恥ずかしいこと」なのだという見えない社会的圧力の方こそ変わらなければならないと思います。むしろ「わかって」しまったら、探求も対話も閉じてしまうのではないでしょうか。
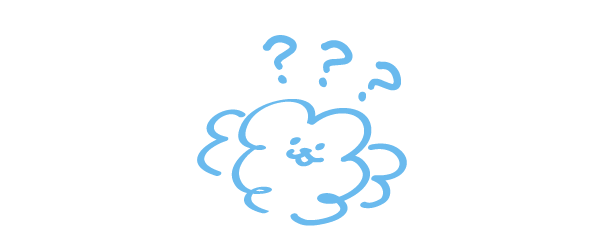
ファストな言葉にあらがう
▶今、言葉のやりとりは、SNSなどのインターネット上にも広がっています。皆さんが寄せてくださった感想には、流行している「論破」やSNSで飛び交う鋭い言葉について、あらためて考えたというコメントも多くありました。
【うちわさん】
哲学は苦手科目でしたが、こういう哲学の形もあるのかと概念を覆されました。 小学生の頃よく「自分って何だろう?」と考え始めると脳の奥底へ沈んでいくと同時に宇宙に投げ出されるような感覚になることがあったのを思い出しました。
問いはどこにでもあり、それについて考えること自体が哲学なのかなと感じました。 「哲学対話」の、最近流行りの「論破」などと違って、相手が言い終えるのを待つ、結論を出さないというやり方も新鮮でした。
連載の中では、特に第6回(編集部注※連載6回目)の「足りない」「さみしい」「問い」に共通点を見いだし、そういうネガティブな感情をスタート地点というポジティブと捉えていく思考が印象的でした。第3回(編集部注※連載3回目)の、絶望の中に勝手に希望を感じ始めるという話とも通じる考え方だなと。
永井さんの著書『水中の哲学者たち』と『さみしくてごめん』も拝読しました。優しくて時に深く、クスッと笑える文章もあり、読みやすくて哲学や哲学者という存在がとても身近になりました。
【なめくじ猫さん】
私は絵を描く仕事をしているので、作業をしているとどんどん自分の内面に落ちて行く感覚があります。でも、その感覚を誰かに打ち明ける機会はゼロに等しいです。その問いを誰かに打ち明けると諍いに発展してしまいそうだからです。若い頃討論や議論をしたくても、爪弾きにされたり陰口を叩かれたりして、そういうつもりじゃないのにな、と思いつつ、自分なりの思想や哲学は心に留めて、空気を読むという処世術を身につけました。多くを語らない方が賢そうに見えたり…。
羽生さんのEchoesを観覧し、永井さんの著書も拝読しました。その後めっきり遠のいてしまった本屋さんに行ってみて、ずらっと平積みされている書籍を眺めてみました。もしかしたら、現代人は自己啓発や最適解だけを求めているのかも、と思いました。現代社会はとにかく忙しすぎる。SNSでもコスパ、タイパのライフハックばかりがお勧めされて来る。テレビはどの時間帯もお笑いノリでおどけて真剣な話をはぐらかす。周りの人は誰かの言ってた言葉を盗んで自分の責任を取らない。考える事、悩む事や迷う事を避けたがっているように思います。
色んな年代の人が哲学対話で真剣に悩む時間はとても貴重だと思いました。感情に任せず、少しでも俯瞰で、多様な見解に耳を傾けてみる。自分の力で考える。みんなで一緒に悩んでみる。ちょっと視界が開けるような気がします。
―多くの人が日常的に使っているSNSのような空間で見られる言葉と、哲学対話の言葉って、どんな違いがありますか?言葉のやりとりについて、一つのあり方のようなものを示せるところはあるんでしょうか?
哲学対話は、SNSが開く世界とはちょっと違うあり方だっていうことですね。SNSって、聞くことがとても難しい。聞けないメディアとも言えます。対話って、発言の奥行きを確かめることだったり、沈黙することも含めて、もっと多様な表現だったりするんですよね。そういう一連の流れの中で文脈を持ったものです。
でもSNSは言葉を断片として取り上げてしまって、その人の声色とか、表情とかがわからない。そうなると、ただただ言葉が連なっているだけにしか見えないところがあって、 よりぶつかるわけです。こういう風に言ったなんてひどい、という風になってくる。でも、SNSでは「うん?」って、引っかかってしまう言葉でも、実際の場で出た言葉には温度感があって、同じ言葉なのに全然違う風に聞こえたり、見えたりすることもあるんですよ。
なので、実際の対話では、聞けるし、一緒にいれるし、もっと知りたいなって、自然に思える。対話って、しぶといし、もがくような時間でもあって、もちろん簡単じゃない。でもSNSのファストな部分にあらがうような時間をきちんとつくることが本当に必要だと思います。

永井玲衣さん略歴
ながい・れい 1991年、東京都生まれ。作家、哲学者。文筆活動の傍ら、学校・企業・寺社・美術館・自治体などで哲学対話を幅広く行っている。2024年には文筆家の故池田晶子(いけだ・あきこ)さんの業績を記念した「わたくし、つまりNobody賞」を受賞した。著書に『水中の哲学者たち』『世界の適切な保存』。新著は『さみしくてごめん』。詩と植物園と念入りな散歩が好き。