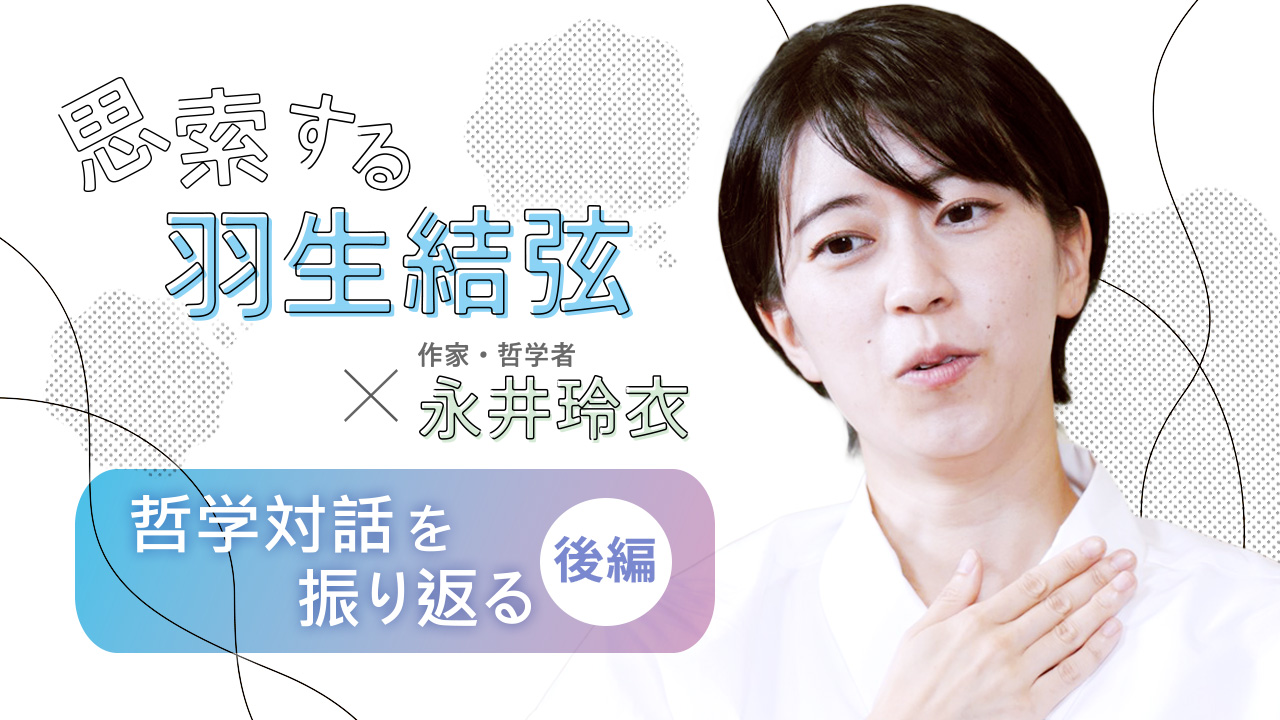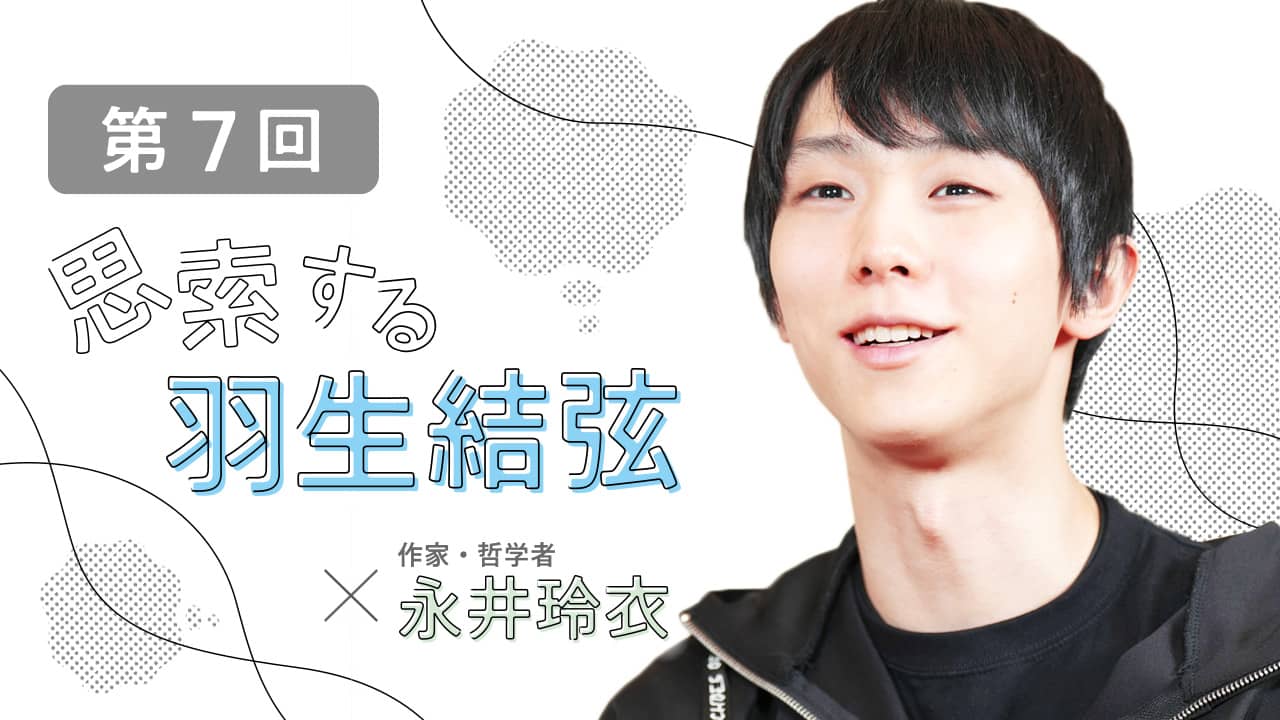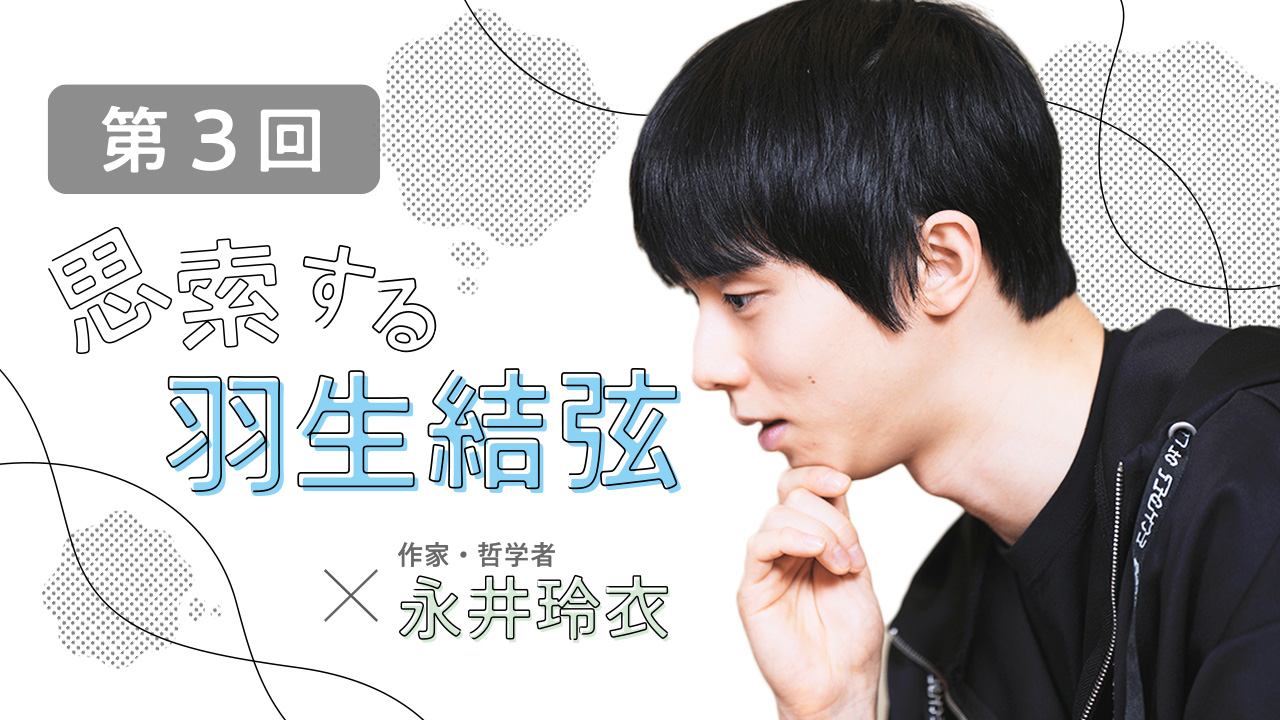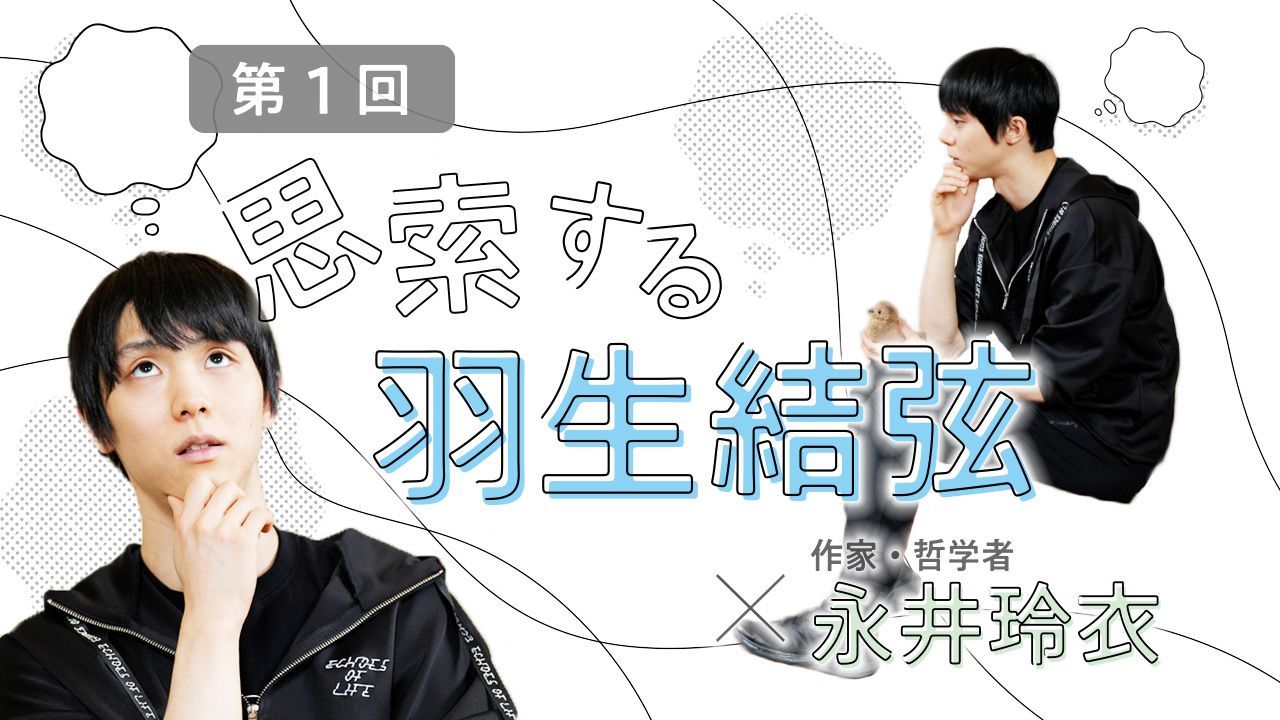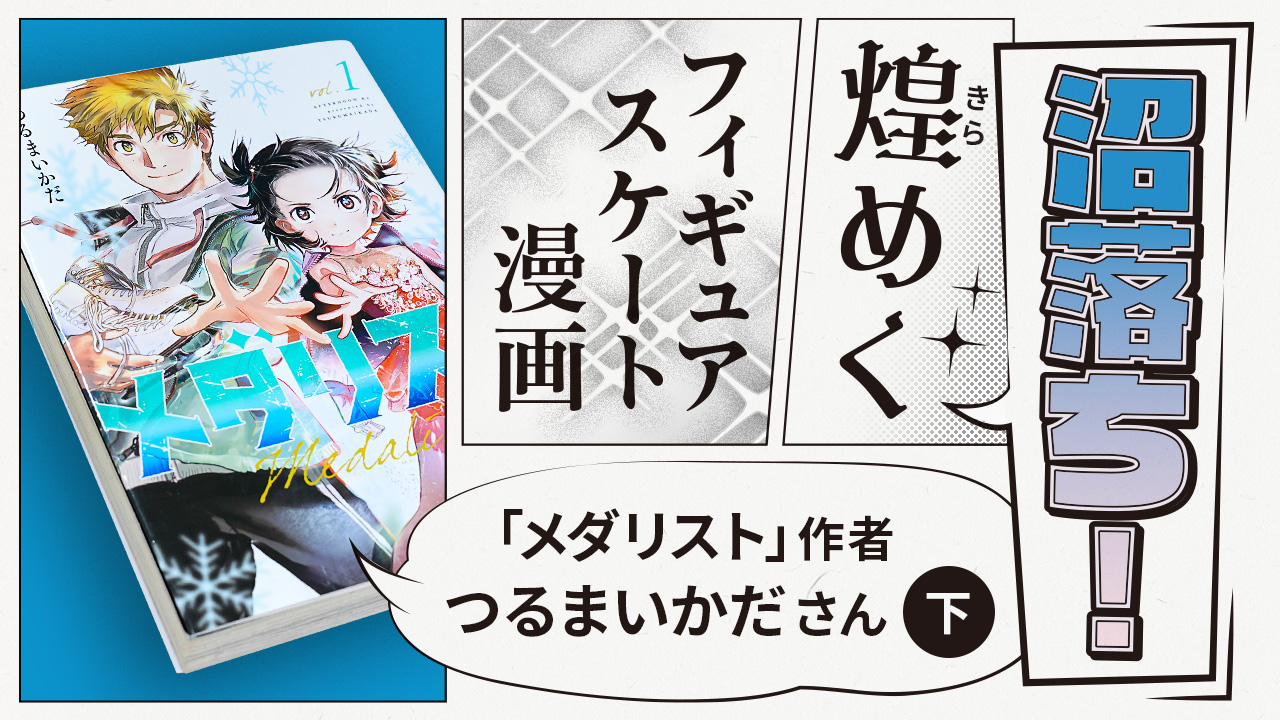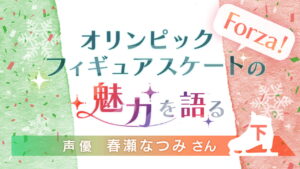「思索する羽生結弦」の連載の第1回の冒頭インタビューで、羽生さんは「すごく大それたことを言うと、日本が良くなっていくというか、世界が良くなっていくに当たって必要なのは、考えること」と話しました。
今回、考えることに希望を感じたり、対話そのものを見つめ直したりした方もいらっしゃいました。また、哲学対話の後半で羽生さんが見いだした「境界線をなぜ引いてしまうのか?」という問いについてのコメントもたくさん寄せられました。
永井さんとお届けする「思索する羽生結弦」感想編の後編です。
互いを人間と思いにくい社会で、声が聞かれる場をつくる
▷羽生さんと永井さんの対話の中に希望を見いだしたり、対話を諦めていたけれど妥協したくないと思うようになったりしたという感想もありました。
【みどりさん】
第一回で羽生さんが「世界が良くなっていくに当たって必要なのは、考えること」と考えていると仰っていたことが、読み進めるにつれ実感として迫ってきて、なんだかそれが私には希望のようでした。
すぐにわかりやすい答えを出すことが望ましいとされる今の世ですが、誰もが問いプードルを抱えて、辿々しくゆっくり語り合い、聞き合い、自問していくほうが、傷つけ合わない世界に近づけるのかもしれないですね。
―永井さんは対話って、希望だと思いますか?
わりと明確に希望だと思っています。私は対話というものを、大げさに考えたいんです。単に楽しいとか、「なんとか思考」のようなメソッドとして、消費していくべきではない。私たちは既に一緒に生きてしまっていて、目の前の他者の声を頑張って聞こうとすることで、社会を変えたり、あるいは共に生きたりすることができる。でも、自分の声が聞かれようとする場は、この社会にはなかなかないので、それを意識的につくっていくことが本当に必要です。
言い方は難しいけど、対話って尊厳と関わっていると思うんですね。相当大げさな言い方をしていますけど、本気でそう思っている。私たちの社会って、互いのことを人間だと思いにくいような、非人間化がすごく進んでいると思うんです。
つまり、たとえば「部長」など、誰かを役割などの記号としてしか見ていなかったり、「◯◯人」という枠組みで見てしまったりしている。でも実際に話を聞いてみると、「あ、この人ってこんなことを考えているんだ」とか、それが別に共感できる、できないじゃなくって、そうか、この人って一人の人間なんだっていうことに出会うわけですよね。
自分自身に対してもそうです。 自分のことを非人間化してる人もたくさんいる気がします。 私なんて考える価値がないとか、あるいはチャットGPTが考えるから私が考えなくてもいいとか。それって、自分のことを大切にできていないことだと思うんですよね。 私が考えても意味ない。だって私の考えなんてしょうもないからっていうことが裏にあるわけです。
でもあなたの考えは、どんなにつたなそうに見えても、あなたの言葉だし、最大限尊重されるべきだと思っています。だから尊厳に関わっているんですが、そういう場があまりにも少ない。あなたの考えは間違ってるとか、しょうもないとか、伝わりづらいとか、そんな風に切り捨てられてしまうような状況で、でも一緒に互いの声を聞き合ったり、誰かの考えを聞いて驚いたりして、もっと広いものが見えてきて、ここに自分がいてもいい、考えてもいいと思えるようになるんですよね。
【はえぐせさん】
全体を通して、自分が今までぐるぐるひとりで考えたり、話せるごく一部の友達と延々話してたことって自分にとっては当たり前だったけど哲学だったんだという気付きがありました。
また羽生さんが最後に仰られたように(編集部注※第7回)、こうやってみんな対話できたら平和な世の中になるのになぁって…常々私も思っていて、 でも、現実は、対話ができない。お互いに対話しようとする意思がないと、対話は成り立たない。すれ違っても対話を重ねられたら理解し合えたり新たな気付きがあったり、問いが生まれたりしてプラスになるのに。
すれ違いを対話せずに怒りに、マイナスに変える人が多い。その現実に妥協して生きていくしかないのかなぁ…と最近は諦めていましたが、連載を読んで、それでもやっぱり諦めたくないなぁとまた思わされました。。
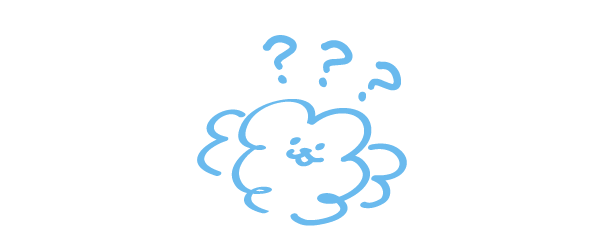
1人で頑張らず、みんなでつくる対話の場
―10年以上、哲学対話をされてきたと思いますが、始めた頃と哲学対話に対する考えは変わりましたか?
だいぶ変わりましたね。始めた時はみんな考える機会がなかなかないから、そういう場があったらいいかなと思っていました。
でも、いろんな現場で教わったのは、みんなすでにすごく考えていたということ。誰もが考えてるっていうことが、本当にシンプルな事実としてあって、その人の言葉や声を持っていました。それが軽視されていいわけがないっていうことを、いろんな場所に行くに従って思うようになりました。
声をより良く聞ける場をどうやって作ろうかとか、それは私一人が頑張るんじゃなくて、みんなでそういう場を作ろうとしあうってことが必要なんじゃないか。そういう発想に変わっていきました。
―考えるっていうことは皆さんが既にしていて、みんなでするっていうことに意識が向いていったっていう感じですか?
そうですね。場っていうのは一人でつくるものじゃなくて、みんなでつくろうとしてみること、試みることだと思うようになったんですね。それができてる、できてないとか、どんな条件を満たせばできるかとか、そういうことじゃなくて、とにかくみんなでやってみようと試みてみる。
最初にあなたの話を聞かせてくださいってお願いするのが自分の立場なんだなっていうことが分かったんです。哲学対話は学生の時に始めて、それまでは、「じゃあみんな集まってください」「こうしますよ」みたいな感じで、場を促進しなきゃいけないのかなって思っていたし、哲学対話に限らず、今も多くのワークショップのファシリテーターってそういうことが求められている。
でも、それでは偉そうだなと思ったんですよ。 私はまず聞き手になりたいというか、あなたの考えていることを本気で知りたいし、教えて欲しい。そういう態度でその場にいたいなって思いました。だから今回のまえがみさんとの対話でも、羽生結弦さんというよりは、まえがみさんが今何を考えているのか本当に知りたい、一緒に考えたいという気持ちでいたなと思います。
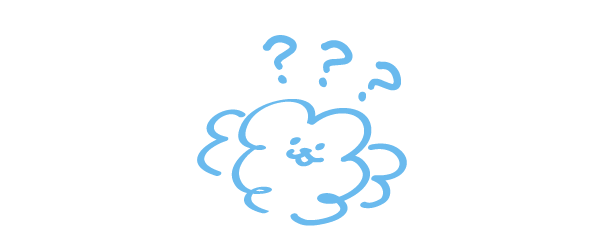
―読者の方には、永井さんの哲学対話にリアルに参加された方もいたとお聞きしました。哲学対話をやってみたいという方もいらっしゃいますが、簡単には参加できません。日常の中ではどんな風にできますか?
羽生さんのファンの方が来られて参加されていました。すごくうれしかったです。 基本的に対話に来ようと自分で申し込むのは勇気がいるじゃないですか。
私は誰もが対話の担い手になれると思っています。すごく大事な場なんだけれども、全く特別じゃないんです。そこが希望なんですね。自分はファシリテーションスキルがないとか、哲学の知識がないからとか、みなさんおっしゃるんですけど、聞くとか、会おうとするとか、待つとか、場を信じるとか、そういう態度を共有していれば、どんな人も担い手になりうるし、なってほしいです。
―今回、羽生さんや永井さんのお考えを伝えたいっていう部分はもちろんありましたが、もやもやしても聞き合っていくような態度のような、そういったことも伝わればいいなと思っていました。
わからなさにとどまるというか、それはわかんないよねって諦めるんじゃなくて、懸命にとどまって、もがいてみる。どっちでもいいじゃん、そういうもんじゃん、人それぞれじゃんって言うのは簡単だし、そっちの方には簡単に行けます。
いろいろな場面で対立が見える今、多くの人が、人の話を聞くことに自信がなくなっちゃってるんじゃないかと思うんですよ。他者が怖い、異なる意見が怖い、自分にはしゃべる能力がない、そもそも考えていない、もう何もできないかもしれない、と。
でも見知らぬ人と出会っても話を聞こうとするってことはできるし、一緒に悩むってこともできるし、結論をまとめないで、一緒に考え続ける。そういうことを選ぶことも、わたしたちにはできるんです。
「境界線」が投げかける問い
▷対話後半の始まりは、羽生さんが見いだした「境界線はなぜ引いてしまうのか」という問いでした(連載第4回)。自分が今いる場所の居心地の良し悪しは境界線とつながっている? 自分が何者かを確認する行為?といった形で、読者の皆さんそれぞれに新たな問いも喚起しました。
【jimmyさん】
この感想を書くにあたり、第五回(編集部注※連載第5回)のねぐせさんの言葉「自分の言葉で話そうとすると、たどたどしくなったり、うまくいかなかったり、、、」の部分がとても刺さりました。
今、書いている感想も「うまくいかない」かもしれません。お読みになっている方に伝わらないかもしれません、、、それでもいいのかな、、、と思いながら書いてみます。印象に残っているのは、「境界線を引いてしまう」ということ。それは、無意識に自分が何者なのかを確認する行為なのかも?
結局「自分」はどんな立ち位置なのかを確認して行動したり、発言したりしているなと思いました。そして気分がネガティブな時ほど、境界線を引きたがるのではと。第六回(編集部注※連載第6回)のまえがみさんの言葉「「わたしたち幸せだよね」って言うときのわたしの輪郭よりも、「わたしたち不幸だよね」って言うときの、「わたし」の輪郭の方が強いのかもしれない、、、」が、あっ!そうだよな!と腑に落ちました。
【くつしたさん】
最近感じていた事はどの情報も信じる事がとても難しくて、メディアもSNSも煽って伝えてしまい過ぎて本質が見えて来ないというか...。 分断するように、そして正解が一つだけのように考えさせない報道やSNSに違和感を感じているところです。
対談の中で「やっぱり人間て、何かを共有したがるんですかね。それこそ、さっきの分配する、境界線がある、境界線をつくるみたいな話って。誰かと何かを共有したいがために、勝手に境界線をつくり始めるっていうか。」(編集部注※連載第4回)と羽生さんがおっしゃってましたが、確かに居心地の良さ悪さは境界線によって生まれているなあと。
私自身どこかに所属しているという安心感とは裏腹に自らの意見を述べるのが怖いと思うのはこの境界線のどこかに入らないといけないと感じる世の中の風潮があるのかもしれないです。
―戦争や社会の分断が起きていて、毎日のように境界線について考える出来事があります。いま境界線について考えていることってありますか?
7月に選挙があって、境界線のことを、いろんな仕方で考えた方がたくさんいたと思います。境界線について一つ想像するのは外部を作る、という意味での境界線ですよね。 今の外国人排斥の流れもそうだと思いますけど、不安ゆえに境界線を引いてしまう。
でも、一度境界線を引くと、不安だからこそ、次に新しい境界線を引くことになります。すでに日本人に対しても「あなたは本当は日本人じゃないでしょう」という線引きが起きていますね。今度は「よい日本人」「悪い日本人」、「より日本を愛している日本人」「そうでない日本人」、境界線はこうやって無限に線を引けてしまう。そうすることによって、じゃあどんな私たちが歴史をたどってきたのかっていうのは明らかです。
境界線として私がいま思うのは、そのことです。対話と境界線の関係で考えると、対話の中で引いちゃった境界線を引き直すこともできます。 今回、印象的な感想がありましたよね。
【アイスバーグさん】
本当に、こんな世の中だからこそ、対話の大切さをしみじみ感じます。意見の違う人を敵対視するのは簡単だけど、そうでなく、対話することがまず第一歩なんじゃないかなと考えさせられました。
印象に残った言葉は「境界線」です。私も常日頃、自分(赤)と、自分と意見の違う人(青)との間の境界線についてよく考えます。これは決して交わらないものなのか、赤と青のままでなく、せめて間に紫の帯を作ることはできないのか、と。それを作るのが対話なのかもしれないということに気づかされました。
決して交わらない。赤と青のままでなく、せめて紫の帯を作ることはできないのかって、すごくすてきな表現だなと思いました。
私たちはみんな同じなわけはなくて、それぞれが異なるんですけど、色は2色じゃないよとか、もっと多様な色があるんだとか、やっぱり境界線って、物事をシンプルにすることなので、もっと複雑だよねってことを対話を通して、そういう世界に入っていくわけですよね。そういう体験をやっぱり対話でできるよってことを言いたいです。
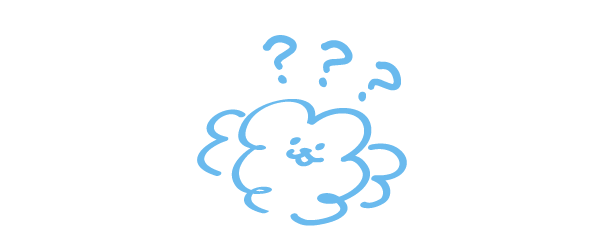
▷子どもの頃、緘黙(かんもく)症だったという方からはこんなご感想をいただきました。
※緘黙症...一般的に選択制緘黙(場面緘黙)と言われ、他の状況では話しているにもかかわらず、話すことが期待されるような特定の社会状況(学校など)では、一貫して話すことができないこと。
【光さん】
小さい頃の私は、緘黙症で話すことが出来なくて。でも、小学校の先生や同級生は、しゃべりなさい。しゃべらないとだめだ!と私を否定し、非難しました。私は、しゃべりたくても、しゃべれない。こんな私は、生きる価値、意味が無いんだと、生きることが苦しかったです。
哲学対話を沢山の方々がしていたなら、沢山の問いを出して、この事を否定することなく、決めつけることなく、いろんな問があるのだと、色んな人がいるのだと、色んな考えがあるのだと思えたのかな!?と思いました。哲学対話を通して、沢山の違いがあることを知ること、そして結論付けないこと。違いを知るきっかけになるのかなと思いました。
第7回(編集部注※連載第7回)最後の羽生結弦選手の言葉「こうやってみんな対話できたら平和な世の中になるのになあって・・・そんな感じです」が胸にズーンと響いています。
―自分にも物語があると気づいたり、自分という境界線を引き直したりする方もいました。
そうですね。いろんな境界線があります。外部をつくるだけではなく、自分の輪郭を伸ばすという境界線もありますし、境界線が常に良くないわけじゃない。でも線を引き直すってこともできるっていうことは少なくとも言いたいです。
線を引いちゃったら、もう終わりなんじゃなくって、人の言葉を聞いて変わったり、色が変わったり、消えたり。じゃあ、別の絵を描いてみようとすることはできるんだよっていうことは伝えたいですね。
▷たくさんのご感想をお送りくださり、本当にありがとうございました。羽生さんと永井さんにお送りいたします。あらためて連載をお読みいただき、ありがとうございました。
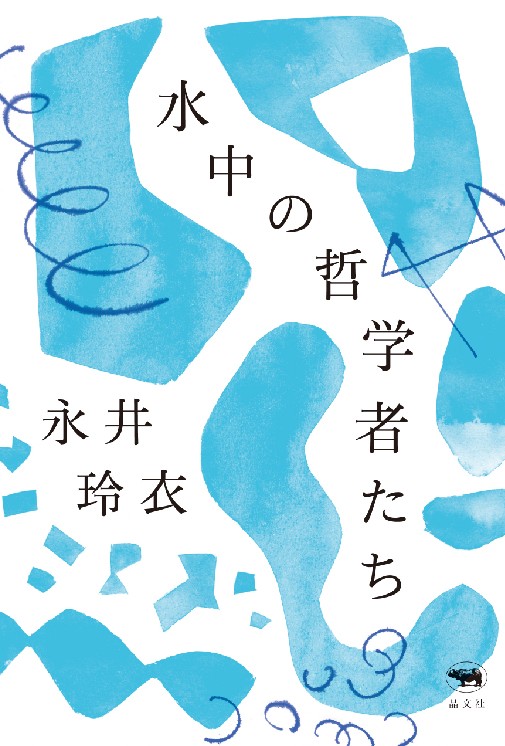
◆晶文社様より永井玲衣さんの本「水中の哲学者たち」をDeep Edge Plus会員3名様にプレゼント◆
永井玲衣さんの本「水中の哲学者たち」を、発行元の晶文社より、抽選でDeep Edge Plusの会員の方3名様にプレゼントいたします。
下のボタンの応募フォームから、Deep Edge Plusの有料会員に登録しているメールアドレスを記載してご応募ください。
締め切りは2025年10月31日です。当選は発送をもってかえさせていただきます。

永井玲衣さん略歴
ながい・れい 1991年、東京都生まれ。作家、哲学者。文筆活動の傍ら、学校・企業・寺社・美術館・自治体などで哲学対話を幅広く行っている。2024年には文筆家の故池田晶子(いけだ・あきこ)さんの業績を記念した「わたくし、つまりNobody賞」を受賞した。著書に『水中の哲学者たち』『世界の適切な保存』。新著は『さみしくてごめん』。詩と植物園と念入りな散歩が好き。